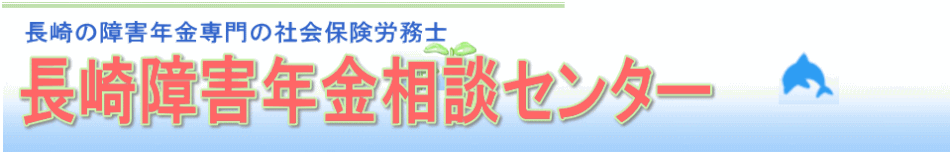(再)審査請求~不支給の決定を受けた時

不支給の決定通知書を受けた時は、不服申し立てができます。
不服申し立ての制度は以下の通りです。
(再)審査請求の制度
年金の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。
その決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求できます。
なお、決定の取消の訴え(行政事件訴訟等)を起こす場合は、原則として、審査請求の決定を経た後でないと提起できません。
ただし、
(1)審査請求があった日から2か月を経過しても審査請求の決定がないとき
(2)決定の執行等による著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3)その他正当な理由があるとき
は、審査請求の決定を経なくても訴えを提起することができます。
この訴えは、審査請求の決定(再審査請求をした場合には、当該決定または社会保険審査会の裁決。)の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告(代表者は法務大臣)として提起できます。ただし、原則として、審査請求の決定の日から1年を経過したときは訴えを提起できません。
(再)審査請求の方法
まず、障害認定基準にしたがい、自分の障害の程度が何級に該当するのか確認します。
次に日本年金機構がどのような理由で、不支給にしたか確認します。
行政文書開示請求を行い、障害状態認定表の開示を求めます。
自分の主張については、明確な根拠が必要です。
たとえば過去の裁決例、日本年金機構のマニュアルや内部文書、専門家会議の議事録、医師の意見書、など必要な種類をそろえます。
日本年金機構の決定は、時には障害認定基準を正しく理解していない場合もありますので、とにかく自分の主張の根拠となる文書をどれだけ揃えられるかが勝負の分かれ目となります。
以上のようなことは、一般の方にとっては非常に困難です。
不服申立の経験が豊富な専門家に依頼する方が、たとえ費用のことを考えても結果的には得です。
(再)審査請求は認められるか
審査請求については社会保険審査官が判断を行います。社会保険審査官は元々日本年金機構の職員であり、大きな期待はでき来ません。
社会保険審査官の拠るべき事務処理要綱すら正確に理解していない審査官も過去にはいました。しかしながら、非常に誠実な審査官もいるのも事実です。
再審査請求に関する判断は、東京の社会保険審査会で行われます。
公開の審理が行われ、6名~8名程度の合議制で決定がなされます。
再審査請求の審理の前に、資料が送付されてきますが、その中に保険者が社会保険審査官に対し述べた意見が添付されていますので、保険者の意見(不支給とした理由)を知ることができます。それだけでも、審査請求より再審査請求の方が、請求人にとって有利と言えます。
いずれにしても、審査請求で1割、再審査請求で1割程度が認容(認められる)されると考えておけばいいでしょう。
障害年金専門の社会保険労務士の中には、自己の実績では6割程度と公言している方もいます。
当事務所も、高い割合で不服申立に成功しています。